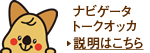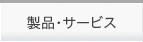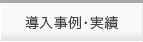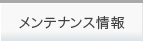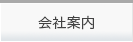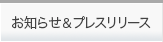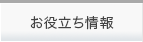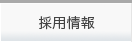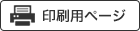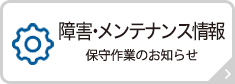ホーム > お知らせ&プレスリリース > 「分岐単位接続料制度の設定」に対する地域アクセス系通信事業者9社合同反対意見について
お知らせ&プレスリリース
「分岐単位接続料制度の設定」に対する地域アクセス系通信事業者9社合同反対意見について
2011年11月30日
東北インテリジェント通信株式会社
| 「分岐単位接続料制度の設定」に対する地域アクセス系通信事業者9社合同反対意見について |
2011年11月30日
株式会社ケイ・オプティコム
北海道総合通信網株式会社
東北インテリジェント通信株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社
北陸通信ネットワーク株式会社
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
株式会社STNet
九州通信ネットワーク株式会社
沖縄通信ネットワーク株式会社
株式会社ケイ・オプティコム
北海道総合通信網株式会社
東北インテリジェント通信株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社
北陸通信ネットワーク株式会社
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
株式会社STNet
九州通信ネットワーク株式会社
沖縄通信ネットワーク株式会社
「分岐単位接続料制度の設定」に対する地域アクセス系通信事業者9社合同反対意見について
弊社共は、自ら敷設した光ファイバを用いてサービスを提供している光インフラ事業者としての立場から、現在「情報通信審議会 ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会」および「情報通信行政・郵政行政審議会 接続委員会」において議論されている分岐単位接続料制度の導入には、断固反対いたします。
1.分岐単位接続料制度の問題点について
弊社共は、分岐単位接続料制度は、以下の2点において解決し難い大きな問題があると考えております。
1点めの問題としては、接続事業者が一部の設備コストしか負担せず、NTT東西殿にコストをつけ回すことが挙げられます。この問題は、接続事業者とNTT東西殿だけの間に留まらず、他の全ての光インフラ事業者が、接続事業者に対して極めて不利な競争を強いられることにあります(図1)。
2点目の問題として、設備を共有することで、どの事業者にも技術革新に対するインセンティブが働かず、その結果、光アクセス網の進化が停滞することが挙げられます。光信号の伝送技術は、現在のものが最終形態ではなく、今後の革新によってさらなる高機能化が期待されますが、技術革新の阻害に繋がる政策の導入により、その高機能化が実現しなくなるおそれがあります(図2)。
一部の接続事業者は、サービスレベル維持や故障対応時のフロー等に対して、NTT東西殿と同じ運用ルールに則った形でOSUを共有する案を希望されていますが、この形態であれば、ISP事業者として「○○ with フレッツ」等のサービスを提供することと同じであり、既に事業参入にかかる環境は整備されていることから、分岐単位接続料制度の設定は全く必要ありません。
また、OSU共有に代わる方法として新たに一部の接続事業者から提案されているGC接続類似機能、ファイバシェアリング、波長重畳接続機能につきましては、今後技術的な検証がなされることと思いますが、大きな追加コストが発生し、その一部をNTT東西殿につけ回す点で、OSU共有による分岐単位接続料制度と同様の問題を有していることから、弊社共は導入に反対いたします。
2.現在の競争状況と制度について
現行の一芯単位接続料制度を活用し、KDDI殿は全国で「auひかり」サービスを展開されており、第18回接続委員会で公表されたデータによると、同社FTTHサービスの加入者は約207万件(2011年9月現在)、市場シェアは8.8%(2011年6月現在)に達しています。この事例が示すとおり、現状においても、競争環境は正当に機能しており、分岐単位接続料制度の導入は必要ありません。
なお、設備更新が停滞するおそれがある点で、弊社共は積極的には賛成しかねますが、希望する接続事業者同士でコンソーシアムを組み、OSUを共用することでFTTH事業に参入することは、原行の制度下でも可能です(図3)。
3.まとめ
現行の制度下で可能な取り組みを十分に検討しないまま、安易に制度変更を行い、公正な競争環境を歪めることは、借りるだけの接続事業者のみ一方的に有利となるだけで、これまで自らリスクを取って設備投資し、地域のブロードバンド化推進に寄与してきた地域アクセス系事業者やCATV事業者の努力を否定するものであるため、弊社共は断固反対です。
合理性のない分岐単位接続料制度の導入は、公正な競争環境を阻害し、設備事業者の事業撤退・縮小を招きます。これは、旧来のNTT独占時代への回帰を意味し、設備競争・サービス競争が起こらなくなります。その結果、価格低廉化が進まず、新サービスも始まらずに、最終的に国民が不利益を被ることになります。
コスト負担のあり方が公正であり、競争条件を歪めない点において、弊社共は現行の一芯単位接続料制度が最も合理的であると考えております。
今後の我が国の情報通信産業の持続的な発展、利用者利便性の向上のためにも、貴省における当該制度の検討においては、弊社共の意見を参考にしていただきたく、何卒よろしくお願いいたします。
以 上
図1:分岐単位接続料制度の問題について(1)
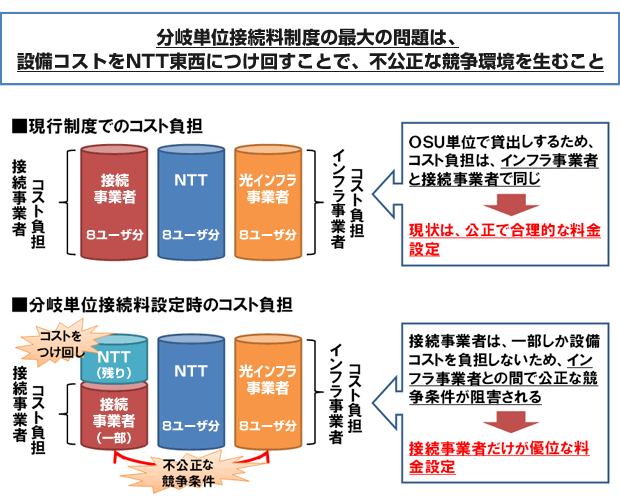
図2:分岐単位接続料制度の問題について(2)
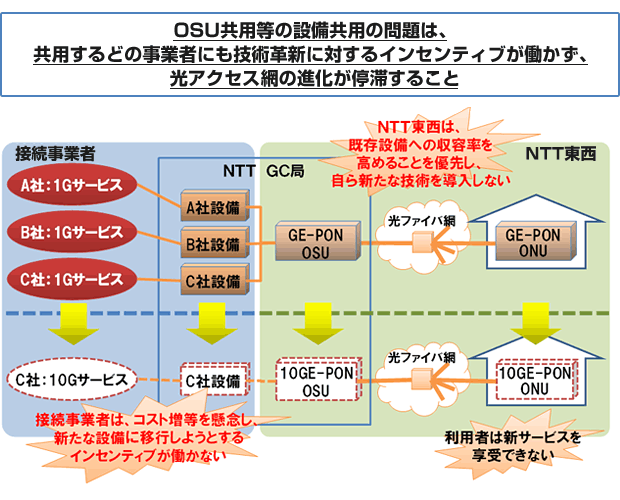
図3:「コンソーシアム方式」での解決
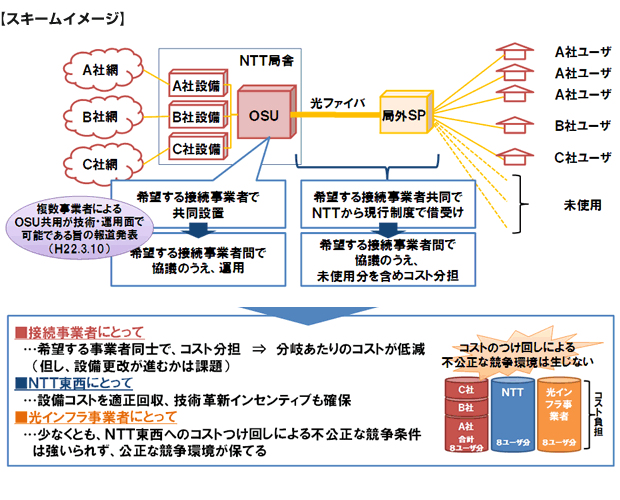
© TOHKnet Co., Inc.